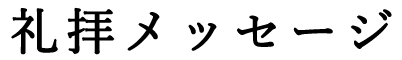我らに祭壇あり
ヘブル13:1-17
本書は、キリストの贖いの優位性、贖いの深さを説いて、私たちに慰めと励ましを与える書だ。「私たちには一つの祭壇があります」(10節a)と言う。旧約時代、モーセが神に示されて造られた幕屋には祭壇があり、そこに犠牲の動物の血が注がれ、その体が焼かれ、贖いの儀式が繰り返されてきた。
しかし、人間の祭司の贖いは不完全で、犠牲を携えて来る人々の罪を完全に取り除くことはできなかった。そこでやがてキリストがこの世に送られた。キリストは十字架にかかって永遠の贖いを成し遂げられた(9:12,14、10:14)。キリストは永遠に変わらない御方であり(8節)、私たちに対していつも真実で、その贖いも不変だ。
ただし、イエスに目を留めていなければ惑わされる(9節)。食物に限らず、富や知識や名誉など、世に属するものに惑わされる。それらは魂の益にはならない。私たちの心を真に強くするのは贖いの恵みだ。永遠の贖いの恵みによって私たちは魂が養われる。「我らに祭壇あり」と言う祭壇とは、その永遠の贖いが成し遂げられたキリストの十字架のことだ。私たちが目を留めるべきは、このただ一つの祭壇だ。
祭壇に献げられた動物の犠牲の血は、幕屋の中へ携えられたが、体は宿営の外へ投げ捨てられた(出29:10-14)。これはイエスの受難を表す。主は都の外で苦難を受けられた(12節)。私たちの王は都の外で十字架にかかられたのだ。そのお誕生の時、客間には余地がなかった。死なれるときも宿営の外だった。私たちは主を受け入れなかったのだ(ヨハ1:11)。
外に捨てられるべきは、罪人の私たちだった。しかし、私たちのために永遠の贖いを成し遂げることを目的として、神の子キリストが宿営の外へ捨てられた。主がまず私たちのために宿営の外へ出られたのだから、私たちも宿営の外に出て主のみもとに行きたい(13節)。居心地の良い所に安住せず、喜んで主のための苦難を身に負う者になりたい。
「いつまでも続く都」「来たるべき都」(14節)とは、前章で述べられた信仰の勇者たちが望んでいたものだ(11:16)。その「都」は、世に属するものからは得られないけれども、この世にあって得られる恵みだ。地上の歩みを営みながら、魂は天の所に移されている生涯を送ることができるのだ。「天の処に座せしめ給えり」(エペ2:6文)という恵み、キリスト内住の恵みのことだ。これこそ私たちが熱心に真剣に求めるべきものだ。なぜなら、地上の生涯の期間は限られているからだ。
私たちがいつまで肉の生涯を続けるか、どれだけ天の所に移された勝利の信仰生涯を歩むかは、どれだけ自己の真相と向き合ったかにかかっている。絶望が深ければ深いほど、激しく渇くものだ。全き贖いを求めていこう。
これほどの深い贖いが与えられたら、与え主なる神への賛美が生まれる(15節)。贖いの目的は、私たちが主をほめたたえることだ(エペ1:6,12,14、詩102:18)。
指導者たちの言うことに聞き従って(17節)、恵みを求めていこう。贖われた民が聖くなることは神の御心だ(1テサ4:3)。
我らに祭壇あり。十字架の贖いを感謝しよう。永遠の都を我がものにしたい。地上のものに心を引かれて、約束を無にしないように心したい。真実に約束を実現してくださる主を信じて、真剣に求めよう。
あなたは祭壇を持っているか。あなたのうちに一つの祭壇が据えられているか。十字架信仰が貫かれているか。主の前に出て探っていただこう。